校内研究の多忙さにより、なかなか投稿ができず、もやもやとした思いを抱えておりましたが、このたびようやく落ち着き、先生ハウスでも共有し、ご意見をいただければと思い投稿させていただきます。今後は、校内でどのような授業が展開されてきたかについても少しずつ紹介しながら、皆様からのご意見を賜りたく思っております。
今回は、私(阿部)が独自に取り組んでいる「自己調整力を育む」ことを意図した授業実践をご紹介いたします。紹介するのは、社会科の学習において、児童が協働しながら問題を解決していく際に活用したワークシートを中心とした授業です。
これまで社会科では、児童が自らのノートを用いて「社会科の見方・考え方」を働かせながら、学習の見通しを立て、学びを振り返ることを大切にしてきました(こちらについては、別途詳しく紹介させてください)。
自己調整学習において重要なのは、①見通しをもつこと、②実行(学習活動)を行うこと、③振り返ること、の3つのプロセスです。
ただし、限られた授業時間内でこれらを実現するには、できるだけシンプルかつ効果的に設計する必要があります。
本校の今年度の研究では、特に「見通し」を、各教科における固有の見方・考え方に基づいて構築することを重視しています。つまり、「学習課題をどのように解決していくか」という“学習方略”に焦点を当てています。本来、自己調整には「情意的方略」なども含まれますが、教科横断的に取り組むにはこのように絞り込むことが有効だと考えました。
実際の授業では、教科書に記載されている課題に対し、児童がまずワークシートの「青い枠」に自身の見通しを書き込みます。教室には、これまでに扱ってきた社会科の見方・考え方が掲示されており、それを参考にすることで、視点を明確にしながら学習に取り組むことができます。
このように見通しを明確にすることで、課題に対して漠然と取り組むのではなく、学習に深みと方向性をもたせることができると感じています。
その後、児童同士で意見を交流し合い、最終的なまとめ(課題の答え)を協働して表現します。今回は「逆ピラミッドチャート」を用い、視覚的に思考を整理しながら、学びを深める工夫をしました。
そして、一番下の青い枠には、「なぜその答えになったのか」「どこに着目したのか」「どのように考えたのか」といった学習の過程を、児童自身が振り返って記述できるようにしています。
これは単に正解にたどり着くことを目的とするのではなく、その過程で用いた「社会科の見方・考え方」に意識を向けさせることをねらいとしたものです。
こうした振り返りを通して、児童が自らの思考プロセスを言語化し、メタ認知的に学習を捉える力を育てていきたいと考えています。

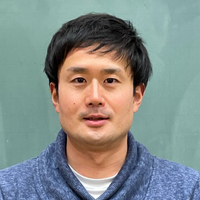
2025/07/24 16:56

