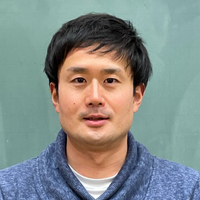自己調整学習はPDCAサイクルを回す学習です。
しかし、今日、PDCAサイクルの課題が指摘されています。
つまり、予測不能な時代において、綿密な計画を行い、実行することよりも、予測し、その予測とのずれを見極め、機敏に対処する力が求められています。
しかしながら、計画し実行することは大切です。
問題なことは、計画に重きを置くというよりは、計画はあくまでもものさしであって、実際に行った際に柔軟に対応する力こそ大切にしていくことだと考えられます。
そこで、注目すべきものとしてPPPサイクルというものがあります。
PPPサイクルとは、以下のようなものを指します。
1. Predict(予測):未来の変化を考える力を養う
概要:過去のデータや経験を基に、将来の展開や変化を予測する能力です。これは、潜在的なリスクや機会を事前に察知し、適切な準備を行うための基盤となります。
2. Perceive(観察知):状況を正確に考える力を育てる
概要:現在の状況や環境の変化を正確に観察し、理解する能力です。 これにより、予測と現実の見通しを認識し、柔軟に対応することが可能となります。
3. Prioritize(優先順位付け):適切な判断をできる下力を養う
概要:複数の課題や選択肢の中から、重要度や度に緊急に応じて優先順位を設定し、効果的に行動する能力です。
以下のような点を重要視していく必要があると考えられます。
①入口よりもその過程を重要視する。
つまり、計画に時間を割くというよりは、まずやってみるということを重要視する。
そのために、ぼんやりでもよいので、直感的な目標、計画を設ける。
②計画を立てたうえで、変更があり、柔軟に対応することが大切であるマインドを伝える。
③優先順位を考えさせる。
例えば、計画通り進んでいない。であれば、教科書の問題をすべて取り組むのではなく、網掛けの問題を行う。
練習問題を行うよりは、メインとなる問題、課題解決に向けて取り組む。
など、自分で調整する力を育てる。
このように、基本PDCAサイクルでありながら、PPPサイクルの要素を取り入れることで、課題となる問題に、臨機応変に対応できる子を育てていきたいと考えています。
細かい考察には至りませんでしたが。今後、具体的な行動レベルで考察していきたいと思います。