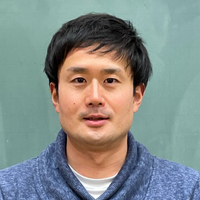「命とはなんですか?」
過去に、子どもたちに「命とはなんだと思いますか?」と聞いてみました。
おそらく人によって定義があるかと思います。
今回は2017年に亡くなったお医者さんの日野原重明さんの命の捉え方を子どもたちに紹介しました。
日野原重明さんは「命とは時間です。」と言いました。
日野原さんは、「生涯現役」をモットーに最後まで精力的に活動を続け、数々の功績や書籍を残しました。
命の授業
日野原さんは実際に学校に訪問し「いのちについて考える授業」を数多く行っていました。
まず、日野原さんは次のように言って授業を始めます。
「自分が生きていると思っている人は手を挙げてごらん。」
子ども達は全員手を挙げます。
「では命はどこにあるの?」と質問すると、心臓に手を当てて「ここにあります。」と答える子がいます。
日野原さんは聴診器を渡して隣同士で心臓の音を聞いてもらって、次のように話を続けます。
「心臓は確かに大切な臓器だけれども、これは頭や手足に血液を送るポンプであり、命ではないんですよ。命とは感じるも
ので、目には見えないんだ。君たちね。目には見えないけれども大切なものを考えてごらん。空気は見える?酸素は?風は見える?でもその空気があるから僕たちは生きている。このように本当に大切なものは目には見えないんだよ」
それから日野原さんは続けて言います。
「命はなぜ目に見えないか。それは命とは君たちが持っている時間だからなんだよ。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。どうか一度しかない自分の時間、命をどのように使うかしっかり考えながら生きていってほしい。さらに言えば、その命を今度は自分以外の何かのために使うことを学んでほしい。」
自己調整学習の中で語る
自己調整学習は、タイムマネージメント、自己との対話があります。
年度末、学習のまとめの学習で、自己採点をすることが多くなります。なまけてしまう心もあるでしょう。
解答を丸写ししてしまう子もいるかもしれません。
頭ごなしに、叱るのはさけたいです。
そこで、命とは時間については話しました。
もちろん、これで自己調整力(時間の調整)が上達するとは限りません。
スキルを習得できるとは思いません。
しかし、人間には心があります。刺激と反応でできていません。
主体性、意思があります。
どのような環境で学ぶか。どのような仕掛けをするとよいか。
たしかに大事です。
しかし、時間とは何か。命とは何か。なぜ、自己調整学習をするのか。
意味を伝えることが大切だと思います。
それをなしに、子どもを学習することは、どこか子どもを子どもとして見ているような気がします。
たしかに、説教くさく、煙たく感じるかもしれませんが、必要なことは伝えたいものです。
だからといって、いつも時間に追われ、大事にしなきゃと気持ちをせかすのではなく、時にはだらっとしてもいい。だって、授かった命だから。
十二分に味わってほしい。
しかし、知らないことで後悔すること、失うこともあるかもしれません。
命とは時間であるといった人がいるんだと頭の隅に入れながら、日々の生活、そして学習の時間を過ごしてほしいと思います。