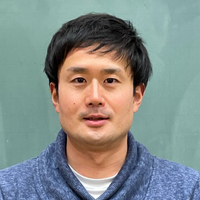どうしてもなかなか「教えて」が言えない子がいます。
それは学級の雰囲気ももちろんあります。
ですから、まずは、学級の土壌を耕すことが大切です。
しかし、それでも言えない子がいます。
多様な子がいるように、多様な指導が必要です。
そのうちのいくつかを上げさせていただきます。
今回は○点上げさせていただきます
①教えるということは、相手が学ぶ大事な機会であることを伝える。
学習したことを説明することは、学びを深める重要なことです。したがって、説明したり教えたりすることは、その人の学びになるということを伝えます。
したがって、助けて、教えてということは、相手のためになることを繰り返し伝えることが大切です。
②となりの人に「教えて」と言う
だれに相談したらよいかわからない場合があります。そこで、基準として隣の人に聞くという基準を示します。
そうすることで、要請される側にも心構えが持てます。
そういうものだというルールが、要請をしやすくなる側面があると思います。
そして、隣の次はグループの人などに、物理的距離を広げていきます。
③ことばではなく、非言語で伝える。
言葉で教えてと言えない場合は、非言語で伝えることもできることを伝えます。
例えば、視線をあげて、助けを求める。
鉛筆を置くなど。
言えなくても、手段があるということを伝えます。
このように心理的なハードルを下げるようにします。
④徐々に、できるようになろうと伝える。
人はすぐに変わりません。ですが、変わることは必要です。
その中間を設置することが必要です。
ですから、今日が3なら、次は4できるように。少しずつ取り組む大切さを伝えることが大切です。
そして、「教えて」と言えない問題は、実は、「教える側」にこそ解決のヒントがあります。
簡単に言えば教える人は、意識のアンテナを高めることが大切です。
つまり、教える人は、周囲を見るということが大切になります。
学びとはというものかを事前に伝えるとより効果的です。学びとはどのようなもので、どのように伝えていくかは、また別で投稿しようと思います。
①周囲をみる
②人の視線、顔を見る
これは、上の非言語を読み取る必要があります。
③えんぴつをもっていない。動いていない。などの温かく見渡す
これだけでかなり変わります。なんとも温かい不運息が
援助要請と援助提供は、相互の気遣いによって成立していると考えます。
そのことは、子ども達にも伝えています。
この様子もモデルで示していきたいと思います。