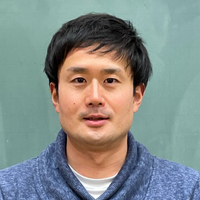今日この頃、教育界では「〇〇な学び」が次々と出てきて、正直ちょっと混乱気味です。現場にいる身として、「わかる〜!」と共感してくださる方も多いのではないでしょうか。
一斉学習がいいのか?
自由進度学習がいいのか?
いやいや自己調整学習こそ最強なのか?
うーん、迷いますよね。
しかも教師が迷えば、当然それは子どもの学びにも直結してしまいます。
…ということで今日は具体的な解決策ではなく、少し哲学に寄り道して考えてみました。
登場するのはハイデガーさん。
その中でも「非隠蔽性(ひいんぺいせい)」という、なんとも舌を噛みそうな言葉をつかって、考えてみます。
要するに「隠れていたものがパッと姿を現すこと」。
真理って「事実と命題が一致する」なんてカチコチしたものじゃなくて、
「ものがふっと現れ出ることなんだよ」と言うわけです。
たとえば授業中。
普段はおとなしい子が、ある問いかけで意外な発言をしてクラスをざわっとさせる。
その瞬間、その子の「考える力」が現れます。
また、テストの点数では見えなかった子の「友達を助ける優しさ」が休み時間に顔を出す。
これも非隠蔽です。
要は、「人にも学びにもいろんな側面があって、その場によって顔を出したり隠れたりする」ということ。
ハイデガーさん、ややこしい言葉を使うから難しく聞こえるけど、実は当たり前のこと言ってるんです。「難しい言葉をつかうなよ」、とすこしイラッとします。
(ただ、当時、彼も苦労していて、ない概念をどのように説明しようか悪戦苦闘したんです。)
さて、学習形態にあてはめると
1 一斉学習では「自分と友達との違い」が見える。
2 自由進度学習では「自分のペースや得意不得意」が見える。
同じ子どもでも、学び方が変われば違う顔が出てくるんです。
だから「一斉」か「自由」かの二者択一で争うんじゃなくて、
それぞれの学びの場で違う非隠蔽(=子どもの姿)が起きていると考えればいい。
教育において、一律な子どもの姿を目指すのではなく、子どもの多面的な姿をどんどん現れさせていくことも大切なのかもしれません。
…ということで今日は、ちょっとハイデガーを借りて考えてみました。
「いやいや、そんなの当たり前だろ!」とツッコミをいただきそうですが、
まあ、コーヒーでも飲みながら「阿部の独り言メモ」として軽く読んでいただければうれしいです。