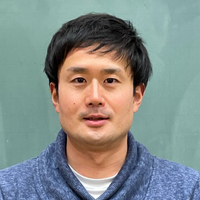今年度の学級通信が91号で終わりました。
これまで200号前後を発行していました。
しかし、今の勤務校では100号までと決まっています。
働き方改革のひとつだと思います。
決まっているので仕方がないです。
今年度は特に、少なめに発行しました。
今回は、自己調整学習に関わる内容を紹介させていただきます。
学習に対する子ども達の心構えになると考えています。
こうしたことを子ども達と共有することで、協働的な学びの心を育てると考えています。
以下は通信の内容です。
勉強は自分のためだけではない
先日の算数の時間、ふと「勉強はだれのためにやるの?」と問いかけてみました。
多くの子ども達は、勉強とは「自分の夢を叶えるため」や、「よい会社に入るため」などと思いがちです。
事実、問いかけると、そのような答えが返ってきました。
しかし、私は子どもたちに、勉強はそういった自分の夢の実現のみならず、「他の人のために行うことでもあること」を話しました。
家ではテレビを見ます。学校ではChromebookというパソコンを使用してます。
つまり、テレビやChromebookを作った人がいます。その人達は、とても勉強をしていることでしょう。専門的なことはもとより、算数や理科の学習をしていることでしょう。
作成している人が勉強しなければ、便利なものは生まれません。
つまり、勉強をしてくれたおかげで、私達は多くのものを使ったり利用したりすることができます。
逆に、自分たちが勉強することで、だれかの役に立つことができます。
勉強したおかげで世の中になかったものを発明するかもしれません。誰かの役に立つことがあるかもしれません。
自分が親となり、子どもに学習を教えるかもしれません。学ぶことで知見が広がり、多くの人の生きる糧を与えるかもしれません。
勉強は自分の問題であると思うと、「自分はだめになってもいいんだ。」「別に、賢くならなくてもいい。」そんなふうに思ってしまいます。なんだかやる気が湧いてきません。
だって、困るのは自分だけですから。
しかし、私は大きな声で「ちがう!」と言いたいです。
子どもたちが学び、これからのリーダーの一人として活躍すること。そして、自らを幸せにするために、勉強するのです。
近い将来、君たち(子ども)を待っている人がいます。君たちの力を必要としている人が待っています。多くの人が、未来で「力を貸してほしい」と願っています。
学習は、自分のためだけでなく、他の人の幸福にもつながっている。また、誰かの力になるために必要なことであると思うと、「ググッ」と力が湧いてくるように感じます。
勉強は自分の問題ではないということを共有することで、なぜ学ぶのか、そしてどのように学ぶのかを考えるきっかけになると思います。