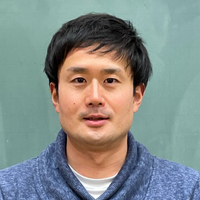これまで、思考スキルの実践について、述べさせていただきました。
一方で、その危険性も留意したいです。
効果的な薬には、副作用があるのと同じで、マイナスの面もしっかりと認識したうえで活用したいです。
『今求められる学力と学びとは: コンピテンシ-・ベ-スのカリキュラムの光と影』 (日本標準ブックレット No. 14) 2015/1/27石井 英真 (著)
に、以下のような記述があります。
「くらべる」(比較)、「似たような場面を考える」(類推)といった一般的な思考スキルの多くは、深く思考しているときに自ずと生じるプロセスから事後的に抽出されたものです。ゆえに、思考スキルを教えたからといって深く思考できるとは限らないし、また、自転車に自然に乗れている人が、なぜ乗れているかを意識しすぎてかえって乗れなくなるように、「思考スキルを使って考える」ということを意識させすぎると、むしろ思考することを害することもあります。特に思考スキルが評価の観点と結びついた場合には、結論・テータ・理由付けで主張が組み立てられているか、ピラミッドチャートやボーン図といった思考のための手立てが効果的に使われているかといった視点で、授業過程の子どもたちのノートの記述や発言を事細かにチェックすることにもなりかねません。思考力を育てるには、考えたくなる状況や深く思考する必然性をどう側るかがまずは重要です。思考スキルは、そうした思考する活動が生起したときに、その経験を自覚化するものとして導入していくことが肝要でしょう。
つまり、思考力とは、考えたくなるような必然性、文脈に即して初めて発揮したり、駆動したりするものです。
それを、ドリル的に抽出したり、押し込んだりすることでかえって思考する際の邪魔になることを伝えてくれます。
したがって、大切なことは思考スキルを身につけることではなく、あくまでも資質能力であって、その過程に自然発生的、必然的に思考スキルが働くという考えが大切だと考えます。
特に、教科特有の学びをしていれば、思考スキルが働かない場合があります。例えば、コンパスの使い方、グラフのかき方などです。
したがって、思考スキルはあくまでも手段。
また、思考のものさしみたいなものにもなるかもしれません。
「あれ?思考スキルが使えない。なぜだ?
そうか違う方法でわかったからか」みたいな感じでしょうか。
どう学んだかを説明することに固執することは学びを空洞化させる危険性もあります。
子どもが遊ぶように、縦横無尽に知の冒険を楽しむことが優先です。その羅針盤や地図のような役割程度で抑えていたほうがいいかもしれません。