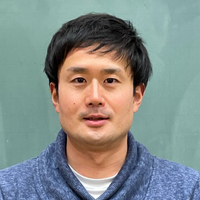たまには哲学的な考察をしてみたいと思います。
硬い文体になってしまいました。読みづらかったら、ごめんなさい。
今年の夏は10本を超える研修を受講しました。その中で「あらためて」強く感じたのは、「学習者をどのように見るか」という視点の大切さです。今回はそれを哲学的に考察してみたいと思いました。これはどなたかへの感想というよりも、自分への戒めとして書いたものです。(もし哲学に関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ対話してみたいと思っています。)
ハイデガーは、従来の「存在への問い」を根本から転換しました。彼の考えは実存主義をはじめ、多くの哲学者に大きな影響を与えています。
簡単に言えば、彼は「存在者(個々に存在するもの)」と「存在(それがどのような世界で存在しているか)」とを区別しました。
従来の存在論的な見方では、たとえば「子ども」という存在を分析し、分解し、属性を整理することが中心でした。
これはある意味で情報処理的なアプローチに近いのかもしれません。しかしハイデガーは、それだけでは不十分だと指摘します。
その子どもを理解するためには、背景――家庭環境やこれまでの学びの経験、つまりその子が生きている「時空の世界」――を抜きにして語ることはできないのです。
要するに、学習者を単なる「入れ物」として捉えるのをやめよう、という提案につながります。
だからこそ、学習方法は一つではなく多様であってよい。そして学習者自身に選択の余地を与えることが大切です。なぜその方法を提供するのか、という問いかけもまた重要です。
私たちが構造的に設計する学習方法は、あくまでも「教師が想定した学習者像」に基づいています。
しかし実際に大事なのは、現にその学習者が自分自身の文脈で生きているということです。学習者には個性があり、声があり、特質があります。そうしたことを踏まえた上で、時には学習方法を提供し、また時には引き下げる柔軟さが求められるのだと思います。
現象学的に言えば、それは「間主観性」という考え方に近いでしょう。つまり、学びには完成がなく、常に変化していくものだということです。
ハイデガーの「存在への問い」から、私はこのように考えました。どうしても子どもたちを「一般化」して見てしまいがちですが、それは非常に危険なことです。
盲目的に、これが正しいのだから、実践する。これは、避けたいものです。
自戒をこめて。