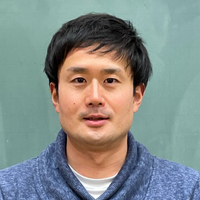自己調整学習などの自律学習において、他者に時間を使うこと、教えることの大切さを具体的に語ることがとても重要なことです。
昨年度私載せた通信の内容を掲載しておきます
子ども達にサイゼリヤの社長の正垣泰彦さんのお話をしました。
( 『16歳の教科書 2 「勉強」と「仕事」はどこでつながるのか (ドラゴン桜公式副読本)』という本の中に、サイゼリヤの社長の正垣泰彦さんのお話が掲載されていました。
正恒さんは、ある日登山をしました。まもなく山頂という時に体がヘトヘトでもう一歩も歩けないほど疲れ切ってしまい、腰を降ろしてしまいました。
しかし、あることがきっかけで、まるで鉛のように重かった腰や足がスッと動き、歩み始めたそうです。
はたして、どうやって歩くことができたのでしょうか。
すると、「他の人に注意された。」や「杖を使った。」、「荷物を降ろした。」などと出てきました。
答えは、同じように疲れ切っている人を発見し、助けにいったことです。それがきっかけで動くことができたそうです。
正恒さんは次のように振り返っています。
「人間って不思議な生き物でね、『自分のため』だけじゃ力が出せないんだよ」
つまり、自分のためではなく、他の人の助けになろうとする時、力が湧き上がってくる。そういうことを実感したそうです。
だから、「自分のために、自分だけに」と考えるのではなく、他の人を助けようと思うことが大切だと、本には書かれています。
この話に続いて私は子ども達に次のように問いかけました。
「ある美容師さんがいました。その方は、当然髪を切ることが得意で、上手です。」
「しかし、ある人だけ、上手に切ることができません。さて、だれでしょうか。」
子ども達は、いろいろと考え、発表していきます。しかし、なかなか答えが出ません。しかし、ある人が、「自分だ!」と答えました。
そう。自分自身の髪の毛を切ることができないのです。自分の手は、もちろん自分のためにあります。自分の手で箸を持ち、ご飯を食べます。しかし、相手の髪を切ったり、背中を流したりするときに大活躍します。他にも、耳。自分の声をボイスレコーダーで再生した時、ものすごく低く感じます。
自分の耳は、自分の声を聞くためというよりは、相手の声を聞くためにありそうです。目もそうです。自分の目は鏡がなくてはどのような形をしてるかわかりません。
相手の顔を見るためにあります。実は、自分の体は自分のためだけにあるのではなく、相手のためにあるのかもしれません。多くの偉人がそうであるように、自分の体を使って他の人のために活躍した事実があります。
精神的に成熟した人ほど、自分の体を他者のために使うことが多いかもしれません。
自分の手を、足を頭をぜひ、いろいろな人のために使ってほしいと思いますし、そういう人になってほしいと思います。
学級通信『歩む』 2024.7.9(火)46号
こうした語りは、さまざまな場面で行っていったり、通信にしたりしていくことで保護者、そして職員室を巻き込んでいくことが可能になります。
今年度通信は91号でした。
現在の勤務校では、100号までと決まっているので、かなり抑えて発行しました。
一時期、1号に5、6枚掲載し続けたことがありました。
これは注意されたのでやめました。
通信は出せばよいというものではなく、精選して出すことを覚えました。
みなさんの語りをぜひ教えてほしいです。