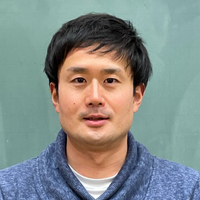本校では、「見通し」と「振り返り」を重視した授業づくりを進めています。
その中で、見通しの段階で自分がどのような視点で課題に取り組むかを明確にすることが、まさに「学習の個性化」につながっていると感じています。
たとえば、国語科の授業で「登場人物の気持ちを考える」という課題に取り組む場合、子どもたちはそれぞれ異なる視点をもつことができます。
・行動に注目して気持ちを読み取る
・会話の内容や言い回しから考える
・情景描写や文脈から想像する
・物語の時代背景や社会状況に着目する
こうした視点は、見通しの段階で共有し合うこともあれば、自分自身の中で整理する時間を設けることもあります。
どの視点で考えるかを自ら選び取ることによって、課題解決のプロセスが個別化され、子どもたちは自分に合った学びの道筋で取り組むことができるのです。
このようにして、一斉授業であっても、「学習の個性化」を図ることができると実感しています。
自己調整学習はプロセスである
自己調整学習は、学習の“形態”ではなく“プロセス”に本質があります。
どのような授業形態であっても、子どもが自分の学び方を意識し、見通しを立て、計画し、振り返る。
こうした一連の流れが大切です。
従来の問題解決型学習の中にも、自己調整的なプロセスを組み込むことは十分可能です。
むしろ、良質な授業はすでにそうした自己調整の要素を自然に含んでおり、子どもたちが自分の考えを深め、他者の視点に触れながら、よりよい学びへと向かっています。
本校でも、「個別最適な学び」や「学習の個性化」といった視点を意識し、日々の授業改善に取り組んでいます。
学びの見通しと振り返りの質を高めることが、結果として、自己調整学習を内包した授業の充実につながると考えています。