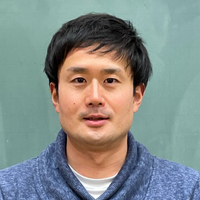「自己調整」という言葉は、単なる学習の枠を超えて、学級経営そのものにも深い影響を与える概念だと感じています。
子どもたちは本来、主体的に学ぶ力をもった存在です。
しかし、人間ですから、時には「やりたくない」「面倒だな」と思う瞬間があって当然です。集中できないとき、気が緩むとき、誰にでもあります。
そんなとき、教師の言葉がけに「自己調整」の視点があるかどうかで、子どもとの関わり方が大きく変わってきます。
たとえば、自習時間におしゃべりをしてしまう子がいたとします。
よくある場面ですが、このときの対応が典型的な例です。
従来型の対応:「おしゃべりはやめなさい」「静かにしなさい」
自己調整的な対応:「集中できないかな?もし休憩が必要なら、少し整えてから戻っておいで」「おしゃべりをしないために、自分なりの方法を考えてみようか」
このように、気持ちのゆらぎや葛藤そのものを受け止めたうえで、子ども自身が「どうしたらよいか」を考えられるよう促すことが、自己調整力を育てる支援になります。
さらに、
「おしゃべりモンスターに勝つ方法を考えてみよう」
などと語りかけることも有効です。
これは茶化しているのではなく、あらかじめ「気持ちモンスター」などの概念を共有しておくことで、子どもたちは自然に自分の内面を客観視し、気持ちと向き合う手立てを探ろうとします。
こうした“自己の気持ちの調整”を、周囲の大人や友達の助けを借りながら身につけていくこと――まさにそれが、学級経営における「自己調整」の真価ではないでしょうか。
子どもは感情を持った存在であり、調子の波を抱えながら日々を生きています。
だからこそ、「ダメなときがあってもいい」という前提に立ち、そのときどうするかを一緒に考えることが、教師の支援の在り方だと思います。
自己調整力は、学力だけでなく、生活や人間関係にも通じる“生きる力”として、これからの教育においてますます重要になっていくはずです。
なお、やろうとしないモンスターについては以前投稿しています。参考になれば幸いです。