これまでの投稿に書きましたが、本校の研究では、児童の自己調整力を育むための授業改善に取り組んでいます。
改めて自己調整学習とは、「見通し」「実行」「振り返り」のサイクルを自ら回し、学習に主体的に取り組むことを指します。
本校では、従来の問題解決学習の形を生かしつつ、その中に「見通し」や「振り返り」を取り入れ、段階的に授業改善を進めています。
今年度(令和7年)の全校研究授業(4年生の先生)では、「見通し」と「振り返り」をコラボノートを活用して実践してくれています。
【コラボノートとは】
コラボノートとは、協働学習支援ツールであり、なじみ深いノートにデジタルならではの機能を搭載したものです。
複数人で同時に書き込みができるのが大きな特徴で、友だちの意見や活動の様子がリアルタイムに画面に表示されるため、動きのあるダイナミックな授業が展開できます。
本時における「見通し」は、コラボノート上で児童が協働編集の形で記入しました。画像(画像は、子どものものではなく、事前研で使ったものです。)の黄色い部分がその記入欄となっています。
緑は振り返りです。
リアルタイムで全員の見通しを一覧することができます。これにより、学習の見通しにおいて「相互参照」が可能となる授業が実現しました。
この取り組みによって、以下のような効果が期待されます。
【児童同士で見通しを共有できる】
他者の見通しをリアルタイムで確認できるため、自分と同じような考えを持つ仲間と相談しながら学習を進めることができます。また、見通しが曖昧な児童も、友達の意見を参考にすることで自らの視点を明確にすることができます。
【主体的・対話的な学びの促進】
ICTの特性を生かすことで、学びの相互参照が自然と促され、児童一人ひとりの学習がより主体的・対話的なものとなります。考えの広がりや深まりが見られ、学級全体の学びが活性化します。
【即時フィードバックの実現】
児童の書き込みを教師がその場で確認できるため、即時のフィードバックが可能となり、学習の方向づけや支援を適切なタイミングで行うことができます。
本校では、今後もこうしたICTの特性を活かし、「見通し」や「振り返り」を効果的に取り入れた授業実践を重ねてまいります。児童一人ひとりが自らの学びを調整しながら成長していく力、すなわち自己調整学習力の育成をめざし、授業改善を進めていきたいと考えています。
なお、今回ご紹介した実践は、私自身の実践ではなく、本校の先生による実践です(掲載については、事前にご本人から許可をいただいています)。
本校では、教職員が互いの実践を学び合い、高め合う風土づくりを大切にしています。
本稿をご覧になって、「こうした方がより効果的ではないか」「この部分の意図はどういうことか」など、ご意見やご質問がありましたら、ぜひコメントやお声かけをいただけたら嬉しく思います。
皆さまからのご意見が、今後の校内研究のさらなる深化につながると思っています。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。
ChatGPT に質問する

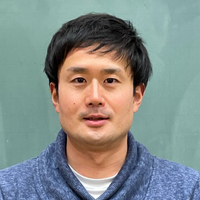
2025/07/29 15:37


