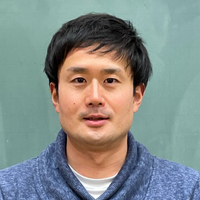本日、管内の大きな研修会に参加しました。
各校の研究部のメンバーが会して、研修が行われました。総勢100名ほど。
講師の方は、元文部科学省教育課程の方。
講演は近年の教育の動向について。
この研修の中で、グループ協議があった。
必然的に自己調整についての話になった。
4名で話し合ったのですが、内4名は自己調整学習という言葉を知らなかった様子です。
たしかに、自由進度学習よりマイナーな感じがします。
しかし1名の方は、来年度自己調整学習を研究で取り入れるらしいです。
とても嬉しかったです。研究紀要など交換する約束をしました。
さて、本題に入ります。
そのうちの年配の方が、自己調整学習の話を聞いて、大変驚いていた。
そして、後半に「他の先生方は、自己調整学習には賛同しているの?」と。
つまり、「子どもがする学習」は頭ではわかるけれど、できるかわからない。
ごもっとものご意見です。
そこで、私は、以下のモデルを示しました。
これは本校の研究で使用したもの。Xでも投稿させていただいた。
つまり、問題解決型学習から自己調整学習への移行プロセスをモデルにしてみました。
本当に驚いていた。
そして、来年度取り入れるという学校の方は、「ぜひ、データがほしい。」といってくださった。
協議の最後には以前投稿させていただいた、系統表と気持ちモンスター(追って投稿しようと思います。)、今回の移行プロセスの3点のデータがほしいと言ってくださった。
嬉しい限りです。
どんどん知ってほしいし、あらゆる教室で展開してほしいと思っています。
上のプロセスはなんだか難しそうに書いていますが、結局は
①準備段階は、従来通り行う。しかし、その展開の中で、自己調整を意識して、学び方、気持ちの方略を意識して指導すること
②初歩段階①は見通す(目標設定)をする。そして、振り返りを行う。
③初歩段階②は見通す、振り返りに追加して、実行するという段階を意識して行うということ。
④中間段階は、3つ(見通す、実行、振り返り)を1時間レベル行ってみる。
⑤最終段階は一単位時間の学習サイクル、単元レベルの学習サイクルを回すというもの。
それを説明したら、ベテランの先生も「それなら、できそう」といってくださった。
人は、新しいことには不安がつきものです。
ですから、やってみようかな。これならできそうかなと思わせることが、現場では大事です。
ドンと示して、やってみるということはできるかもしれませんが、できない方もいることを考慮していくことが、みんなでやる難しさであり、新しい道を見いだすものです。
一人の百歩より、百人の一歩を目指したい。